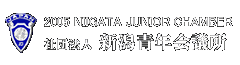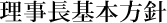
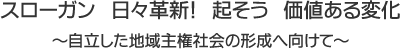
1. 基本方針
昨年(社)新潟青年会議所は時代の大きな変革期の中、創立50周年という大きな節目を迎えました。そして、本年、我々は、50年という輝かしい歴史と諸先輩方が築き上げられた礎のもと、これからの時代に求められる次の「明るい豊かな社会」の実現へ向け、新しい50年をスタートします。
そのため、今年度を50周年に掲げた「新潟JC宣言」を着実に実行する10年の起点としての1年目として位置付け、今後の具体的活動方針を明確にするべく取り組む1年間とします。あるべきまちの姿を想像し、Jayceeとして、市民として、そして企業人としてまちづくりに参画し、にいがたをよりすばらしいまちへと発展させ、次代へ繋いでいくこと、それが51年目に課せられた我々の大きな使命であると認識しております。
<自立した地域主権社会の形成へ向けて>
混沌とした時代の中、ここ近年情報技術の革新的変化は、情報量の増大と時間や距離を越えた広域的な共有化を生み出し、地球規模で社会や経済を捉えることを可能としました。
情報は集めるものから選択するものになり、どこに進むべきかの可能性は拡大したものの、どのように進むべきかは、我々や地域自らが方針を定め、方策を選択し、活路を見出す時代になってきたと言えるのではないでしょうか。
また、ここ10年間を見た場合、都市インフラには大きな投資がなされ、まちの景観は大きく変わりました。しかしながら、一方でそれら都市インフラを有効活用するソフト作りは地域の重要課題として依然残されているように思えます。
このような環境下において、我々は、にいがたが本州・日本海側最大の地方都市から、独自性をもった存在感ある自立した都市へとその存在価値を高め、かつ、にいがたの地域アイデンティティを明確に示す機会として広域合併を捉えると共に、2007年の政令指定都市以降を視野において、これからのにいがたづくりに取り組んでいくことが大切であると考えます。
それらに取り組む糸口の一つは、にいがたのアイデンティティである「食」(米、酒、海産物)と「環境」(水の都、日本海、信濃川、森林、田園、雪)という地性を活かした、それらを包括的に捉えた戦略的な産業育成と、それを強力に推し進める市民の主体的な地域づくりへの参画が、自立した地域主権社会形成へ向け重要であると認識できるのではないでしょうか。
そして近い将来、日本地図が大きく塗り替えられ、道州制に移行することが現実視されています。道州制移行後のにいがたを共通の言葉で思い描き、その役割を明確にし、にいがたという地域の存在感を示すべく、計画的で実効性のあるJC運動の展開が必要であります。
<JCの価値を高める地域と調和した運動の展開>
JCの本質的な価値は、地域に根ざした世界的な青年経済人のネットワークから生み出される、志に基づく地域づくりの実践と、それを通して得る人間性の成長にあります。そして、その価値を支えている要因は柔軟な発想と変化に対応できる青年としての若さであり、方向性を明確にして、多くの仲間と共に行動できる組織の結束力といえるのではないでしょうか。
本年は、このようなJCの本質的価値をより高め、公益法人としての存在意義をしっかりと認識し活動するために、諸先輩方が築いてこられた多くのネットワークをより深く理解し、JCに対して社会が求める視点から、行政、JCと社会活動領域を共有するNPOやまちづくり団体やそして市民と共に、まちの未来と地域課題を共有し、共に解決に取り組める「協働の場」を創出します。
この「協働の場」を通じて、より地域と調和した運動を展開することで、自立した地域主権社会の形成への第一歩とすべく取り組んでまいります。
<社会起業家としての生き方>
自立した地域主権社会形成へ向けて、JCとしてどのような人材開発に取り組むべきなのでしょうか。地域の自立が求められる今、時代を的確に捉え、地域のために貢献できる人材として社会起業家に注目し、育成すべく取り組んでまいります。
地方分権一括法は、大筋で「国と地方行政の役割を変え、より地域のニーズや実情にあった活力ある地域づくりを住民参加のもとに主体的に取り組むこと」を示しています。
このような地域づくりに必要な方向付けと課題を的確に捉え、最も効果的な社会サービスを戦略的に実現するべくリーダーシップを発揮し、実践する人が社会起業家であります。
社会起業家にはまず能力として「地域課題」を認識し、「リーダーシップ」を発揮でき、「こと」を効果的に進められる「経営資質」や「戦略」が必要です。また、環境として「経営資源」「組織的対応力」「有益な人脈」があり、それに割ける「時間」や「コスト」を負担できなければなりません。これほど社会起業家に求められる資質が備わっている人材が多い組織はJCの他にないように思えます。
そして地域課題を「新しい価値の創造」や「現在の事業の革新」を通して自らの事業の社会性を高めていくという、社会起業家としての側面を合わせ持つことに注目すべきではないでしょうか。
本年は一人ひとりが社会起業家としての側面を認識するために、地域課題を見出し、それを具体化した社会起業プランの作成を行います。そして社会に貢献できる事業であるかをJC内部だけではなく、外部からも評価をしていただき、にいがたに新しい価値をもたらすための事業を実施します。
そして社会事業プランを作成するプロセスにおいて、「社会起業家としての能力を磨くこと」=「企業経営者としての能力を磨くこと」であるという認識を促します。
それ故、社会起業プラン構築においては、厳しいビジネス同等の視点や評価が必要であること、そして社会起業家と企業経営者の資質向上には何も差は無く、その違いは自己の企業と顧客に留めるか、地域社会に具体的な成果として広げるかの差であると認識できるはずです。
この認識を持ち活動することが、自分自身や企業に対し、そして地域社会に対して価値ある変化をもたらすものであり、そこにこそJCの社会起業家としての側面を強化推進する意義があるのです。
<日々革新しよう>
JC運動は諸先輩方の礎のもと、大きな成果を生み出してきました。それはまちづくり、ひとづくりであり、そして50年の歴史に裏付けられた志ある運動が生み出してきたネットワークです。
その志を受け継ぎ、より高い成果を生み出していくためには、JC三信条を基に、メンバー相互の本質を認め高め合い、一人ひとりが共にこれからの時代に合う組織をつくり上げていく意識を高めていく必要があります。
そのためには、「参画することが自分自身を成長させる」こと、そして「自分自身、企業、地域に価値ある変化を起す」という共通の認識を持ち、一人ひとりが地域のリーダーとして成長していくことが大切です。
成長に欠くことのできない「考え」「発言し」「行動し」「反省する」というプロセスを計画的に重ねて、日々革新できる自分作りを目指していきましょう。
志ある「JCマン=社会起業家」の集団であり続けるために
さあ、英知と勇気と情熱を持って、失敗を恐れず戦略的に行動していきましょう!
|